さて米人2人に言わせると、日常生活で聞こえてくるJ-Popに入ってくる英語のフレーズは、時折非常に心の平安を乱すものである、とのこと。今回はこのあたりについて考えてみたい。
そもそも、なぜ日本語の歌に英語のフレーズが入っているのか。まず思いつくのは、
・英語のフレーズを入れることで、かっこよさ、クールさ、おしゃれその他を表現できる。
・日本人が英語に対して憧れに近い感情を持っており、英語のフレーズを入れることで歌詞の格が上がる、といったら言い過ぎだろうが、ともかく、日本語オンリーよりも良くなる、と考えている。
・もう一つ思うのは、洋楽のエッセンスを取り込みながら進化してきたJ-POPは、そもそも英語のフレーズと親和性が高い、なんてことはないかな。演歌のメロディには英語のフレーズは合わないだろうが、J-POPのリズム感は演歌よりも洋楽に近いために、英語のフレーズを入れるという誘惑から逃れられない、なんて仮説はどうだろうか。無理があるか。
・知人から指摘を受けたのだが、英語にすることで表現をあいまいにできる。「愛しています」というよりも「I love you」という方が婉曲的表現である。なるほど。それはあるかも知れない。逆に日本語では言いにくいことを、(婉曲的だからこそ)英語ならストレートに言える、ということもあるかも知れない。
それでは、なぜこういう英語のフレーズが彼らを不快にするのか。彼らと話をしながら考えてみた。
・発音やアクセントがめちゃくちゃ
先日彼らに聴いてもらった歌は英語圏に向けた歌だったが、日本で流れている歌は日本人に向けた歌。すなわち、英語として日本人に認識されればOKで、それ以上は必要ない。米人にちゃんと伝わるように歌うのも大変なのに、何の努力もしなかったら、そりゃ良く伝わらないわな。
・歌の中に分かる言葉が突然出てくる。それも時には間違った文法で、時にはキュートすぎ(Miss youとか、Stay with meとか、内容がシンプルすぎ、というか幼稚)。例:「すぐに会いたくてもう一度oh baby(西野カナ Dear...)」
・英語だけでは意味が通らない。前後の日本語の歌詞と合わせた一文で意味が成り立つということは何となく彼らに分かるが、それがどういう意味か分からない。(だからよけいに気になる)。これは分かる。ま、実際には必ずしも英語のフレーズと前後のフレーズがまとまって一文になっている、ということはなさそうだ「約束はいらないLove Forever(清水翔太×加藤ミリヤ)」。
Case Study:
全然分からない歌の中に知っている単語が突然出てきて、それが文法的にも変だったらどう思うか。とある日本語の歌で、英語の部分を日本語に、日本語の部分を伏せ字にすると、米国人の気持ちがある程度分かるはず。こういう歌を耳にしたときにどう思うか、みんなで考えてみたい。
XXXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXX
彼女は美人を持つ 顔 彼女は美人を持つ 顔
XXXXXXX XXXXX
彼女は美人を持つ 顔 彼女は美人を持つ 顔
XXX XXX
ニューヨーク ニューヨーク XXXX XXXXX
ニューヨーク ニューヨーク XXX XXXXX
ちなみに歌詞サイトでは「She has a beauty face」と言っている。「She's a beauty face」と書いてある歌詞サイトもある。どっちにしろ微妙だ。
ところで、英語と日本語を比べると、日本人は英語に対する憧れのようなものを持っているのではないか、それで日本語の歌に英語のフレーズが入る、と書いた。それならば、英語と別の言葉はどうなのか、よく英語と米語は違うと言うが本当なのか。最近は日本のアーティストがアジアで人気と聞くが、だとすると、現地の歌に日本語のフレーズが入っていたりするのか。次回はそのあたり、すなわち歌から見る言語間のヒエラルキーについて調べてみたい。


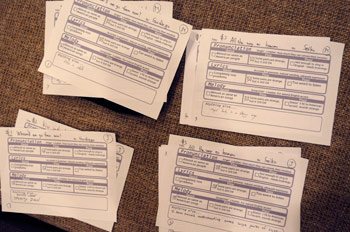















最近のコメント